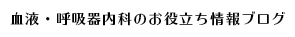お勧めの一冊:風の軌跡(堂島翔)
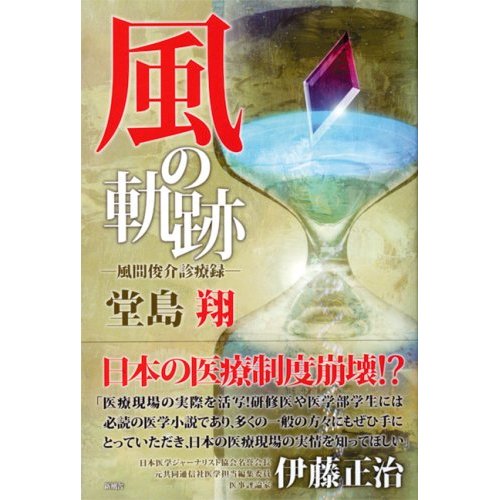 今回は、お勧めの一冊をご紹介したいと思います。
今回は、お勧めの一冊をご紹介したいと思います。
小説「風の軌跡」(堂島翔)です。
堂島翔はペンネームですが、ご本人を存知あげています。
とても真面目に医療に取り組んでおられる内科医です。
医療を深く考えさせてくれる一冊ですが、同時に人間関係や恋愛なども巧みに描かれていて、ぐ〜っと引き込まれていきます。
医療関係を学んでおられる学生さんや、研修医のみなさんにとっては、医学の勉強にもなるかも知れません。
とは言っても決して堅苦しい本ではなく、楽に読み進めることができます。
実は第三内科の医師や、事務職員、研究助手の方にもご紹介したのですが、大変評判が良くご家族の方も読まれているようです。
是非、全国の医療関係を学んでおられる学生さんや、研修医のみなさんにお勧めしたいです。
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 10:22 | 研修医/学生用ミニセミナー | コメント(0) | トラックバック(0)
出血に強い人間が現代に生き延びたが。。。
 人間は出血に強い生物です。
人間は出血に強い生物です。
古代の人間は、狩りをして事故にあい、天災害に遭い、縄張り争いをして、多くの外傷を経験するなか、出血のため多くの人間が命を落としたと思います。
古代の人間が生き延びるためには、高度に発達した止血機能(血を止める働き)が必要だったでしょう(※:人間が出血に強い理由は下記)。
逆に止血機能が不十分な人間は、淘汰されていったに違いありません。 そういう過程を経て、現在に生きる我々子孫の止血機能はとても強力です。
しかし、現代に生きる人間は、狩りもしませんし出血する機会が大変少なくなりました。 そのために、高度に発達した止血機能はかえって邪魔になっています。 なぜなら、止血と類似の機序(血小板と凝固因子の作用)によって血栓症(脳梗塞、心筋梗塞など)も発症してしまうからです。
遠い遠い将来の人間は、高度に発達した止血機能を持った人間は淘汰されて、 止血機能が不十分な(若干出血はしやすいが血栓症にはなりにくい) 選ばれた者たちの時代がくるのではないでしょうか 。
(※)人間が出血に強い理由:
1)血小板や凝固因子と言った止血因子が、本当に必要な量の数倍〜10倍もあります。たとえば、血小板数の正常値は20〜40万です。血小板数が1/10に低下すれば3万ですが、血小板数が10万に下がっただけでは出血しません。
特発性血小板減少性紫斑病(ITP)の患者さまで、血小板数3万で無治療外来通院中の方が多数おられますが、ほとんど出血はありません。あるいは、血友病Aの患者様でも、第VIII因子が10%もあればほとんど出血することはありません。
2)凝固ガスケードの存在。学生さんや、研修医の皆さんにとってはおそらく見たくもない凝固のカスケードですが、この何段回もあるカスケードによって、凝固反応は飛躍的に増幅されます。初めはわずかな凝固活性化であっても、最終的には強力な凝固反応となって、止血いたします。
なお、画像は、福井県立恐竜博物館(勝山市)HPからの引用です。
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 09:34 | 医学全般 | コメント(0) | トラックバック(0)