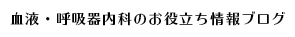【医師国家試験過去問題】下肢の腫脹
医師国家試験過去問題
25歳の男性。突然の左下肢全体の腫脹と疼痛とを主訴に来院した。昨夜、飲酒後に就寝したところ、明け方に痛みのため覚醒し、次第に左下肢が腫大してきた。体温36.5度。下肢に明らかな感染巣を認めない。左下肢は腫脹し、一部暗赤色の発赤を認める。最も考えられる病態はどれか。
a. 特発性浮腫
b. リンパ流障害
c. 深部静脈血栓症
d. 血小板減少に伴う出血
e. 凝固因子異常に伴う出血
この臨床問題には、さりげなくキーワードが多数散りばめられている。
(キーワード)
1) 突然:脳梗塞、心筋梗塞、肺塞栓などの血栓症を連想しても分かるように、血栓症の重要なキーワードの一つに、突然発症がある。
2) 左下肢の腫脹:両側ではなく、片側のみである点がポイント。ある日突然、片側下肢のみの腫脹といえば、もう回答となる疾患くらいしか思いつかないかも知れない。
3) 前日の飲酒:これはあまり直接関係ないかも知れないが、飲酒は利尿作用があり脱水の原因になる。そのため、血液粘度が上昇し血栓症を誘発する懸念がある。
4) 体温36.5度:敢えて書いてあるのは、感染性疾患ではないという暖かいヒント。加えて、感染巣がないとまで念押しがある。
5) 一部暗赤色の発赤:血流遮断に伴って、血液が血管外にリークしたためと考えられる。
(答)C
(内科専門医試験対策)
深部静脈血栓症の危険因子
1)脱水・多血症
2)肥満
3)妊娠
4)下肢骨折・外傷、手術
5)下肢麻痺、長期臥床、ロングフライト
6)癌
7)心不全、ネフローゼ症候群
8)経口避妊薬
9)深部静脈血栓症や肺塞栓症の既往
10)血栓性素因
11)その他:近年、話題になりやすい地震災害時の深部静脈血栓症/肺塞栓も理解しておく必要がある。地震災害時には、脱水、ストレス、不動(車中泊を含む)が、誘因となっている。弾性ストッキングの装着が勧められる。
(血液専門医試験対策)
深部静脈血栓症の血液学的血栓性素因
1.先天性凝固阻止因子欠乏症
アンチトロンビン欠乏症
プロテインC欠乏症
プロテインS欠乏症
2.線溶異常症
プラスミノゲン異常症、高Lp(a)血症
(Lp(a)は、線溶因子であるプラスミノゲンと類似した構造を有し、拮抗的に作用する)
3.後天性血栓性素因
抗リン脂質抗体症候群
(抗カルジオリピン抗体、ループスアンチコアグラント)
高ホモシステイン血症
特に、抗リン脂質抗体症候群は不育症(習慣性流産)とも関連して、出題されやすい。抗リン脂質抗体症候群の治療は、ワルファリンが有効というN Engl J Medの報告があるが、催奇形性の副作用があるため、挙児希望の女性には処方できない。
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 06:40 | 医師国家試験・専門医試験対策 | コメント(0) | トラックバック(0)
【医師国家試験過去問題】血友病A&von Willebrand病
金沢大学第三内科(血液内科・呼吸器内科)の試験問題対策の記事を連載する旨の予告をさせていただきましたが、まずは、手始めに、医師国家試験(過去問題)の解説から開始したいと思います。
医師国家試験・専門医試験対策のカテゴリーへ。
上記のカテゴリーから入っていただきますと、 実際の過去問題解説は、かなりページをさかのぼる必要があるのですが、よろしくお願い致します。
特に、金沢大学での過去問解説や、血液内科(血栓止血領域)の国試対策記事を充実させています。金沢大学血液内科試験では、医師国家試験での高得点につながるような思いを込めて作題していますので、国試対策にもなると思っています。
【医師国家試験過去問題】血友病A&von Willebrand病
血友病Aとvon Willebrand病とに共通しているのはどれか。
a. 遺伝形式
b. 主な出血部位
c. 出血時間延長
d. APTT延長
e. 血小板粘着能低下
血友病
疾患概説:先天性の出血性素因で、関節内出血や筋肉内出血といった深部出血を特徴とする。血友病Aは先天性の第VIII因子欠損症、血友病Bは先天性の第IX因子欠損症である。
遺伝形式:血友病A&Bともに伴性劣性遺伝であり、男性のみに発症する。
検査所見:血友病A&BともにAPTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)が延長する。PT(プロトロンビン時間)、出血時間は正常。血小板機能(血小板粘着能、血小板凝集能を含む)は正常。
治療:血友病Aは第VIII因子製剤、血友病Bは第IX因子製剤。
合併症:
1) 血友病Aでの第VIII因子インヒビター(血友病Bでの第IX因子インヒビターもありうるが低頻度)。
2) HIV&HCV感染症:20数年以上前に、凝固因子製剤を使用した症例で問題となっている(薬害)。
専門医試験対策:インヒビターが出現した場合の対応は、バイパス製剤。近年は、遺伝子組換え活性型第VII因子製剤(商品名:ノボセブン)の使用頻度が増加している。
von Willebrand病(フォンヴィレブランド病、旧:フォンビルブランド病)
疾患概説:先天性の出血性素因で、鼻出血などの粘膜出血を特徴とする。先天性に、von Willebrand因子(vWF)が低下している。
遺伝形式:最も多いtype Iは常染色体優性遺伝であり、男女ともに発症する。
検査所見:出血時間とAPTTが延長する。PTは正常。
血小板粘着能が低下する(vWFは血小板の粘着に必要)。
第VIII因子活性の低下(vWFは第VIII因子のコファクターであり、vWFが存在しないと第VIII因子は安定して血中に存在できない)
治療:コンファクトF(純度が高くないためvWFも含有した第VIII因子製剤)、DDAVP(血管内皮からvWFを放出させる作用がある)(国試既出)
専門医試験対策: DDAVPは連用すると血管内皮中vWFのストックがなくなるため、効果が減弱する。血液専門医試験では、von Willebrand病のサブクラスに関する出題も予想される。
(国家試験対策)
血友病A&von Willebrand病は、必ず毎年出題されている。基本的知識で回答できる良問が多い。この手の問題は、絶対に落とさないようにしよう!
(確認)
出血時間の延長が見られるのは、以下の3つの場合のみである。
臨床的には、もっぱら血小板機能のスクリーニング(下記の2))目的に行っている。血小板数が低下していれば出血時間は当然延長しているため、敢えて行うことはない。
1) 血小板数の低下:各種血液疾患など。
2) 血小板機能の低下:血小板無力症、von Willebrand病、Bernard-Soulier症候群、アスピリンなどのNSAIDの内服、尿毒症など。
3) 血管壁の脆弱性
(答) d
医師国家試験・専門医試験対策のカテゴリーへ。
医師国家試験 問題対策のエッセンス記事:血液内科(血栓止血領域)へ
【参考記事】
研修医の広場(金沢大学第三内科) ← 当科での研修の様子をご覧いただくことができます。
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 06:20 | 医師国家試験・専門医試験対策 | コメント(0)