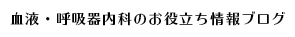金沢大学 血液内科・呼吸器内科(検索順位)
ホームページ通称:金沢大学 血液内科・呼吸器内科
ホームページ正式名称:
金沢大学附属病院血液内科・呼吸器内科・細胞移植学講座(旧第三内科)
上記ホームページ(このブログは上記HPに併設)を、2008年9月11日にリニューアルオープンさせていただいてから、10日を経過しました。
私達にとっては、「血液内科」「呼吸器内科」「研修医募集」などの主要キーワードで、GoogleやYahoo検索でどのあたりに掲載されるか気になるところです。
検索順位は、1日どころか時間単位でも変動することがありますが、今日の只今の時点での記録を残しておきたいと思います。
「血液内科」での検索:Google 18位/1,380,000件
「血液内科 研修医募集」での検索:Google 11位/61,100 件
「呼吸器内科」での検索:Google 11位/831,000 件
(3nai.jpで掲載されますが当科のことです)
「呼吸器内科 研修医募集」での検索:Google 7位/65,000 件
まだ、リニューアルオープンして間もないにもかかわらずこの成績はかなりの善戦ではないかと喜んでおります。
特に、「血液内科」または「呼吸器内科」の単独キーワードでも、検索2ページ以内に登場するのには管理人も驚きました。
試しに、「血液内科 呼吸器内科」を検索しましたら、1位/365,000 件でした。私たち医局の血液内科と呼吸器内科が力を合わせると、日本一になれるということだと解釈しています。
検索順位に恥ずかしくないように、今後ともますます研鑽を積みたいと思っているところです。
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 22:26 | その他 | コメント(0) | トラックバック(0)
【金沢大学統合卒業試験過去問題】兼:国家試験対策・専門医試験対策
金沢大学統合卒業試験過去問題(2005年)
(設 問)
67歳女性。約10年間の糖尿病治療歴がある。5日前より頻尿と排尿時痛を自覚。昨日より39℃を超える発熱、食欲低下、口渇がみられるようになり来院した。意識清明。血圧126/82。肋骨脊柱角に叩打痛を認める。血液学的検査:白血球 14,200、赤血球 386万、Hb 12.2g/dl、血小板 2.5万、クレアチニン 1.4mg/dl、LDH 274単位(基準176〜353)、PT 13.8秒(基準10〜14)FDP 41μg/ml(基準10以下)。なお、血液培養にて大腸菌が検出された。
適切な治療薬はどれか。 予測正答率 80%
( )a 利尿薬
( )b ビタミンK
( )c ヘパリン類
( )d 新鮮凍結血漿
( )e 副腎皮質ステロイド薬
(ポイント)
1) 本症例は、膀胱炎から急性腎盂腎炎を発症した症例で、血液培養の結果より菌血症をきたしている。
2) 血液検査のうち、血小板数、FDPの成績から、播種性血管内凝固症候群(DIC)を合併していると考えられる。
3) Hb、クレアチニン、LDHより、血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)、溶血性尿毒症症候群(HUS)は否定的。
4) PTが延長していないことより、ビタミンKの欠乏もない。
5) DICに対してヘパリン類の投与が適切である。
6) なお、脱水状態にあると考えられることから利尿剤は不適当である。また循環不全はなく、糖尿病があることから副腎皮質ステロイド薬は不要である。
(内科専門医試験対策)
DICの基礎疾患は熟知している必要がある。基礎疾患を有する症例に遭遇したら、DICの合併の可能性を考えて検査を行うところが、診断の第一歩となる。以下が、代表的なDICの基礎疾患である。
敗血症、急性白血病、固形癌、産科合併症(常位胎盤早期剥離,羊水塞栓)、外傷、熱傷、膠原病(血管炎合併)、ショック、大動脈瘤、劇症肝炎、肝硬変、急性膵炎など。
特に、敗血症、急性白血病、固形癌は、DICの三大基礎疾患である。
(血液専門医試験対策)
DICの病型分類、分子マーカー(TAT、PIC、PAI、Dダイマーなど)の変動について、最小限の知識は必要である。
治療に関しても、アンチトロンビン濃縮製剤、ヘパリン類の種類は知っている必要がある。抗線溶療法は原則禁忌である。
詳しくは、ホームページのNETセミナー(DIC病態・診断、DIC治療)へ。
(答)C
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 20:18 | 医師国家試験・専門医試験対策 | コメント(0) | トラックバック(0)
【金沢大学統合卒業試験過去問題】兼:国家試験対策・専門医試験対策
金沢大学統合卒業試験過去問題(2007年)
(設 問)
34歳女性。流産の既往が3回あり。現在内服中の薬物なし。昨夕より、左下肢の腫脹が出現するようになった。本朝になり左下肢の腫脹が悪化し、疼痛による歩行困難もみられるようになったため来院した。血液学的検査:白血球 8,200、赤血球 362万、Hb 12.2g/dl、血小板 8.5万、ALT 23単位、クレアチニン 0.8mg/dl、LDH 214単位(基準176〜353)、PT 11.2秒(基準10〜14)、APTT 73.4秒(基準対照32.2)、FDP 16μg/ml(基準10以下)、CRP 5.8 mg/gl(基準0.3以下)。
この患者にみられる検査所見として誤っているのはどれか。1つ選べ。
予測正答率 85%
( )a Dダイマー上昇
( )b フィブリノゲン上昇
( )c 抗カルジオリピン抗体陽性
( )d von Willebrand因子活性低下
( )e ループスアンチコアグラント陽性
(ポイント)
1) 本症例は、習慣性流産の既往を有する女性で、血小板数低下とAPTT延長をきたしており、抗リン脂質抗体症候群が強く疑われる。
2) 左下肢の腫脹、炎症反応(CRP上昇)、FDP上昇は、深部静脈血栓症(DVT)を発症したためと考えられる。
3) DVTのため、FDP同様にDダイマーは上昇しているものと考えられる。
4) フィブリノゲンは炎症反応の一環として上昇しているものと考えられる。
5) 抗リン脂質抗体症候群と関連して、抗カルジオリピン抗体およびループスアンチコアグラントは陽性であって良い。
6) von Willebrand因子活性は、炎症のためむしろ上昇しているものと考えられる。
(内科専門医試験対策)
抗リン脂質抗体症候群(antiphopholipid syndrome:APS)とは、臨床症状があり、診断用検査1)2)3)のいずれか一つ以上が陽性の時に診断される。
臨床症状
1) 動脈血栓症 and/or 静脈血栓症
2) 不育症(習慣性流産)
診断用検査
1) ループスアンチコアグラント
2) 抗カルジオリピン抗体
3) 抗β2GPI抗体:日本では保険点数はついていない。
良く見られる検査所見(必ず見られる訳ではない)
1) 血小板数低下
2) APTT延長
3) 梅毒反応の生物学的偽陽性(BFP)
4) 抗核抗体陽性
5) 複数凝固因子活性の低下
(血液専門医試験対策)
ループスアンチコアグラントや、第VIII因子インヒビターなどの循環抗凝血素の存在下では、凝固時間のクロスミキシング試験(混合試験)で、凝固時間の延長が補正されないのが特徴である。
例:
患者血漿(Pt)APTT 73.4秒
コントロール血漿(C)APTT 32.2秒
混合血漿(Pt:C=1:1)APTT 69.0秒(凝固時間の延長が補正されていない):ループスアンチコアグラントや第VIII因子インヒビターなど(ただし、第VIII因子インヒビターでは2時間incubationが必要)。
混合血漿(Pt:C=1:1)APTT 38.0秒(凝固時間の延長が補正されている):血友病や肝硬変などの凝固因子欠乏状態。
(注意)
クロスミキシング試験(混合試験)は、ごく最近保険収載された検査項目であるため、血液専門医試験や内科専門医試験などで特に出題されやすいものと推測される(混合試験のデータの解釈など)。
(答)d
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 07:20 | 医師国家試験・専門医試験対策 | コメント(0) | トラックバック(0)