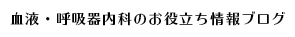第10回 日本咳嗽研究会(金沢)
 第10回 日本咳嗽研究会
第10回 日本咳嗽研究会
日時 : 2008年11月1日(土) 15:00〜19:00
場所 : 金沢市アートホール
〒920-0853 金沢市本町2-15-1(ポルテ金沢6階)
TEL:076-224-1660
1. シンポジウム(pro & con)
「慢性咳嗽の診断治療は的確に行われているか」
2. Chronic cough : up to date 2008
「基礎と臨床」
当番世話人は、当科の石川県済生会金沢病院 呼吸器内科 小川晴彦先生生です。
第一回 1999.10.23 東京 経団連会館 藤村政樹(金沢大学)
第二回 2000.10.7 大阪 ホテルグランヴィア大阪 新実彰男(京都大学)
第三回 2001.10.6 名古屋 エーザイ東海サポートセンター 内藤健晴
(藤田保健衛生大学)
第四回 2002.10.5 東京 エーザイ別館 内田義之(筑波大学)
第五回 2003.10.4 新潟 ホテル日航新潟 藤森勝也 (新潟県立加茂病院)
第六回 2004.10.9 札幌 アートホテルズ札幌 田中裕士(札幌医科大学)
第七回 2005.10.8 秋田 さとみ温泉 塩谷隆信(秋田大学)
第八回 2006.10.14 神戸 新神戸オリエンタルホテル 石田春彦
(前 神戸大学、谷口耳鼻咽喉科)
第九回 2007.11.10 大阪 大阪国際会議場 東田有智(近畿大学)
第十回 2008.11.1 金沢市アートホール 小川晴彦(石川県済生会金沢病院)
プログラム
<開会の挨拶にかえて> 15:00〜15:10
座長 石川県済生会金沢病院 呼吸器内科 小川 晴彦 先生
— 日本咳嗽研究会10年の歩み —
日本咳嗽研究会代表世話人 金沢大学付属病院呼吸器内科 藤村 政樹 先生
<一般演題> 15:10〜16:10(発表5分、討論5分)
座長 石川県立中央病院呼吸器内科 西 耕一 先生
1)「咳喘息患者に対する抗ロイコトリエン薬と長時間作用型β2刺激薬の効果比較」
東京女子医科大学第一内科 横堀 直子 先生
2)「マイコプラズマ感染症による咳嗽が遷延する機序解明へのアプローチ —遷延咳嗽抑制に有用な鎮咳薬の検討— 」
聖マリアンナ医科大学呼吸器・感染症内科 渡邉 直人 先生
3)「咳喘息患者のimpulse oscillometry (IOS) 所見と健康関連QOL:
軽症喘息患者との比較検討」
京都大学 医学部 呼吸器内科 竹田 知史 先生
座長 神戸大学大学院医学系研究科呼吸器内科学 西村 善博 先生
4)「慢性咳嗽患者および健常人におけるメサコリン誘発咳嗽の検討」
金沢大学附属病院 呼吸器内科 大倉徳幸 先生
5) 「慢性咳嗽で発症したブロンコレアの一例」
半蔵門病院アレルギー呼吸器内科 小柳 久美子 先生
6) 「通年性アレルギー性鼻炎患者の後鼻漏と咳嗽」
藤田保健衛生大学 医学部 耳鼻咽喉科学教室 長島圭士郎 先生
〈休 憩〉 16:10〜16:20
<Annual Review; Chronic cough up to date 2008> 16:20〜17:00
座長 熊本大学大学院医学薬学研究部環境分子保健学分野 高濱 和夫 先生
基礎・・・・・ 星薬科大学薬学部 薬物治療学 亀井 淳三 先生
座長 三重大学医学部附属病院呼吸器内科 田口 修 先生
臨床・・・・・ 秋田大学医学部附属病院 保健学科 塩谷 隆信 先生
〈休 憩〉 17:00〜17:10
<PRO&CON> 17:10〜18:50
テーマ 慢性咳嗽の診断治療は的確に行われているか
1)ACは慢性咳嗽の診断治療に重要な疾患概念か?
座長 新潟県立柿崎病院 呼吸器内科 藤森 勝也 先生
PRO・・・富山市民病院 呼吸器内科 石浦 嘉久 先生
CON・・・京都大学医学部附属病院 呼吸器内科 新実 彰男 先生
2)PNDSは慢性咳嗽の診断治療に重要な疾患概念か?
座長 藤田保健衛生大学 耳鼻咽喉科・気管食道科 内藤 健晴 先生
PRO・・・兵庫県立こども病院 耳鼻咽喉科 阪本 浩一 先生
CON・・・福井大学 耳鼻咽喉科 山田 武千代 先生
<閉会の挨拶にかえて> 18:50〜19:00
座長 国立病院機構相模原病院副院長 臨床研究センター長 秋山 一男先生
—アレルギー性気道疾患における環境真菌の重要性—
第10回日本咳嗽研究会当番世話人 石川県済生会金沢病院 呼吸器内科 小川晴彦 先生
◆ 会終了後情報交換会を準備いたしております。(会場:ホテル日航金沢4階 鶴の間)
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 10:01 | 学会・地方会 | コメント(0) | トラックバック(0)
オルガラン(ダナパロイドナトリウム)とは:ヘパリン類
Danaparoid sodium(ダナパロイドナトリウム)
ダナパロイドナトリウム(商品名:オルガラン)は低分子量ヘパリノイドであり(分子量5,500)以下の成分から構成されています。
ヘパラン硫酸84%、デルマタン硫酸12%、コンドロイチン硫酸4%(ヘパラン硫酸が主成分である)。
抗Xa/トロンビン活性比が非常に高く(22倍:標準ヘパリンは1倍)、血中半減期が相当長い(20時間:標準ヘパリンは0.5〜1時間)ことが特徴です。
標準ヘパリン、低分子ヘパリン(low molecular weight heparin:LMWH)(商品名:フラグミンなど)同様に、アンチトロンビン(AT)依存性に抗凝固活性を発揮し、主としてXaを阻止します。
日本における保険適応は、播種性血管内凝固症候群(DIC)のみですが、欧州においてはヘパリン起因性血小板減少症(HIT)、深部静脈血栓症(DVT)に対して頻用され好成績が報告されています。
血中半減期が長い特徴を生かせば、24時間持続点滴で患者を拘束したくない慢性DIC症例、術後早期離床を促したい患者における術後DVT発症予防などで最も有用性を発揮できるものと考えられます。
注意点:
1)腎代謝のため、腎機能低下症例では用量を減じます。また、抗Xa/トロンビン活性比が高いと出血の副作用が少ないと言われてはいますが、万一出血した場合には半減期が長いことがデメリットになることもありえます。
2)管理者らは、腹部大動脈瘤や肝巨大血管腫に合併した線溶亢進型DIC(慢性に経過)に対して、ダナパロイドナトリウムとトラネキサム酸の併用療法を行い、患者のADLを損なうことなく優れた効果を発揮した症例を経験しています。また、抗リン脂質抗体症候群(APS)患者における習慣性流産に対しての臨床試験がおこなわれた上で、適応が是非欲しいところです。
<以下、全てリンクしています>
参考記事(フラグミン、クレキサン、オルガラン、アリクストラ):ヘパリン類
NETセミナーも参照:DICの病態・診断、DICの治療
Ontachi Y, Asakura H, et al: Kasabach-Merritt syndrome associated with giant liver hemangioma: the effect of combined therapy with danaparoid sodium and tranexamic acid. Haematologica. 2005 Nov;90 Suppl:ECR29.
Ontachi Y, Asakura H, et al: Effect of combined therapy of danaparoid sodium and tranexamic acid on chronic disseminated intravascular coagulation associated with abdominal aortic aneurysm. Circ J. 2005 Sep;69(9):1150-3.
【関連記事】
<特集>播種性血管内凝固症候群(図説)← クリック(シリーズ進行中!)
関連記事(リンクしています)
・ヘパリン類(フラグミン、クレキサン、オルガラン、アリクストラ)
・低分子ヘパリン(フラグミン、クレキサン)
・オルガラン(ダナパロイド )
・フサン(線溶亢進型DICに対する特効薬)
・リコモジュリン(トロンボモジュリン製剤)
・NETセミナー:DICの病態・診断
・NETセミナー:DICの治療
・NETセミナー:血栓症と抗血栓療法のモニタリング
・プラビックス:パナルジン、プレタール、プロサイリン、ドルナー、ワーファリンとの比較(納豆は大丈夫か?)