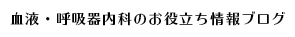急性期DIC診断基準 vs. 旧厚生省(厚労省)DIC診断基準
【はじめに】
播種性血管内凝固症候群(disseminated intravascular coagulation: DIC)は、基礎疾患の存在下に持続性の著しい凝固活性化をきたし、全身の主として細小血管内に微小血栓が多発する重篤な病態です。
旧厚生省研究班疫学調査によりますと、DICの死亡率は60%程度と報告されており、予後改善のためにも適切な診断の意義は大きいと考えられます。
下記もご参照(クリック)いただければ幸いです。
【旧厚生省(厚労省)DIC診断基準】(長所と短所)
我が国では、旧厚生省(厚労省)DIC診断基準が現在まで長年にわたって使用されています。今も日本で最も頻用されている診断基準です(NETセミナー:表1)。
● 長所:
典型的なDICで見られる臨床所見・検査所見を列挙し、スコアリングすることで客観的にDICを診断するのが長所です。
用いられている項目は、1)基礎疾患の存在、2)臨床症状(出血症状・臓器症状)、3)FDP、4)血小板数、5)フィブリノゲン、6)プロトロンビン時間(PT)です。
● 短所:
臨床症状が出ないとDICと診断されにくいことです。
また、特に感染症に合併したDICではフィブリノゲン低下がまず見られないこと、PTはDICよりも肝予備能低下やビタミンK欠乏症の要素で延長することが少なくないことなども問題点と考えられます。
このため、DIC早期診断には不向きとの指摘が多いです。
【急性期DIC診断基準】(長所と短所)
● 長所:
急性期DIC診断基準には、いくつかの特徴があります(NETセミナー:表1)。
まず血小板数において、経時的な要素を取り入れた点です。経時的要素を取り入れたDIC診断基準はこの基準が世界初です。
また、救急領域で遭遇しやすい敗血症に合併したDIC(線溶抑制型DIC:FDP上昇が軽度にとどまることが多い)を想定し、FDPが軽度上昇であっても高スコアを得られるようにしている点も特徴です。このため、感染症に合併したDICの診断には威力を発揮します。
● 短所:
急性期DIC診断基準は白血病群には適応できません。
また、SIRSの概念は救急領域では浸透しているものの内科領域ではなじみにくいこと、感度上昇を求めた反面として特異度が低下している懸念があることは短所と考えられています。
また、前述のようにPTは、DICの要素よりも、肝不全(肝予備能低下)やビタミンK欠乏症の要素で変動することが少なくありません。PTはDICの診断には不要ではないかという指摘があります。
【理想的なDIC診断基準へ】
既存の全DIC診断基準に共通の問題点があります。それは、DICの本態は著しい凝固活性化ですが、これを評価するマーカーが含まれていないことです。
この点、TATなどの凝固活性化をみる分子マーカーを診断基準に組み込みたいところです。
また、線溶活性化の程度がDIC病態に大きな影響を与えるため、何らかの形でPICなどの線溶活性化マーカーを取り入れたいところです。
管理人らの私見ですが、たとえば急性期DIC診断基準からSIRS項目を割愛し、PTに代わってTATなどの凝固活性化マーカーを組み込んではどうかと考えています。また、補助診断項目(DIC病型分類用)として、PICなどの線溶活性化マーカーを採用したいです。
診断基準は誰でもどこでも使用できる基準にすべきとの意見も一理あるのですが、むしろ有用な分子マーカーを積極的にDIC診断基準に取り込むことで、これらのマーカーの普及と医学レベルの向上につながるものと確信しています。
診断基準は誰でもどこでも使用できる基準にすべきという意見だけでは、100年経っても診断基準の発展はないのではないかと思っています。
DIC関連記事(リンクしています)
・播種性血管内凝固症候群(DIC)の病態、診断、治療(研修医/学生対応)
・急性前骨髄球性白血病(APL)とDIC:ATRA、アネキシンII
・NETセミナー:DICの病態・診断
・NETセミナー:DICの治療
・ヘパリン類(フラグミン、クレキサン、オルガラン、アリクストラ)
・低分子ヘパリン(フラグミン、クレキサン)
・オルガラン(ダナパロイド )
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 05:13 | DIC | コメント(10) | トラックバック(0)