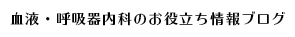研修医の歓迎会
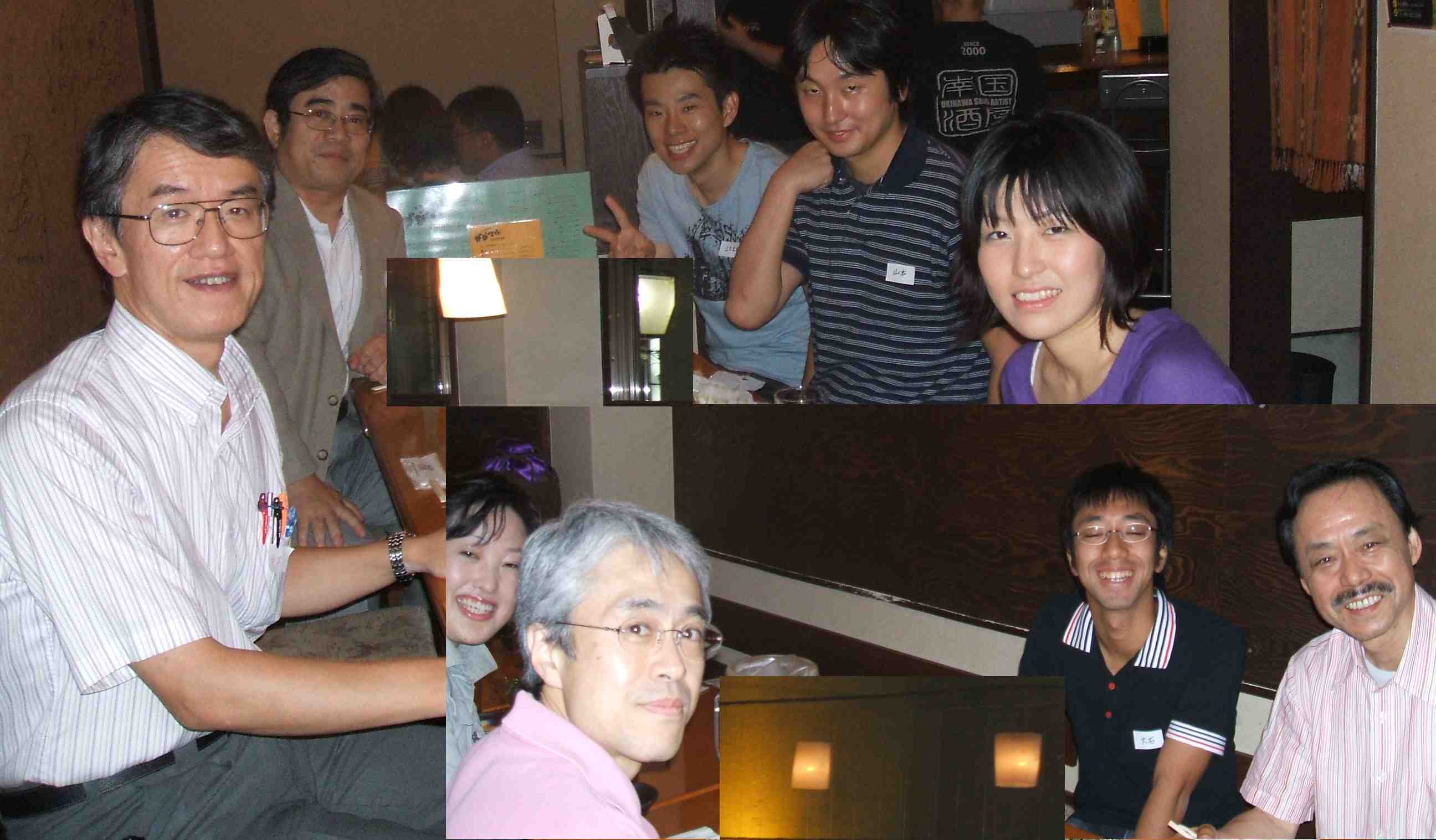
平成20年9月25日(木)午後7:30〜
当科への研修医の歓迎会が開催されました。
BSLの学生さんたちにも合流していただいています。
遅めの時間での開始だったため、集合写真が撮れませんでした(写真を合成して集合していただきました)。1〜2割の方しか写っていないと思います。写らなかった方には、お詫びいたします。
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 23:30 | その他 | コメント(0) | トラックバック(0)
【金沢大学統合卒業試験過去問題】兼:医師国家試験・専門医試験対策
金沢大学統合卒業試験過去問題(2007年)
(設 問)
36歳女性。全身皮膚の点状出血のため来院した。
現病歴:1週間前から感冒様症状、食欲低下が出現するようになり、近医にて抗生剤を含む投薬を受けた。3日前から四肢、胸腹部などに、点状出血がみられるようになった。本朝から鼻出血が出現し、止血しないため来院。
既往歴:特記すべきことなし。
現 症:意識は清明。身長158cm、体重56kg。体温36.4℃。脈拍88/分、整。血圧122/82 mmHg。鼻出血、歯肉出血あり。四肢、胸腹部に点状出血が多数みられる。心音、呼吸音異常なし。腹部は平坦で、肝、脾、腎を触知しない。下肢に浮腫を認めない。
検査所見:赤血球340万、Hb 10.5g/dl、白血球6,700、血小板1.2万、PT 18.4秒(基準10〜14)、APTT 39.6秒(基準対照32.2)、フィブリノゲン320 mg/dl(基準200〜400)、FDP 7μg/ml(基準10以下)、ALT 28単位、LDH 284単位(基準176〜353)、クレアチニン 0.6 mg/dl 、CRP 0.1 mg/dl(基準0.3以下)。ハプトグロビン正常。PIVKA II陽性。
本症例の治療として、誤っているのはどれか。1つ選べ。
予測正答率 85%
( )a 血漿交換
( )b ビタミンK点滴静注
( )c ピロリ菌の除菌療法
( )d 免疫グロブリン製剤投与
( )e 副腎皮質ステロイド薬投与
(ポイント)
1)本症例は、特発性血小板減少性紫斑病(ITP)が疑われる。
2)また、PT延長、PIVKA II陽性よりビタミンK欠乏症を合併しているものと考えられる。
3)ハプトグロビン正常、LDH正常より溶血の所見はなく、特発性血小板減少性紫斑病(TTP)は考えられない。血漿交換はTTPの治療である。
4)ビタミンK点滴静注は、合併しているビタミンK欠乏症の治療として適している。
5)c、d、eは、いずれもITPの治療として適している。なお、選択肢cであるが、ITPに対する除菌療法は急性期ITPに対する治療としてではなく、慢性期ITPに対する治療として行われることが多いことをふまえて、直前に他の選択肢に差し替えました(何に差し替えたかは記憶していません、すいません)。ただし実際の臨床の場では、急性期ITPであっても、除菌療法が行われることは少なくないです。
(内科専門医試験対策)
ITP治療の第一選択と言えば、一昔前は、ステロイド療法、第二選択は摘脾術でした。しかし、現在は、その考え方に変化が見られてきています。
ピロリ菌陽性の患者様では、除菌療法をまず考えます。わずか1週間の除菌治療で、しかも副作用はほとんどありません。ステロイドは長期間服用が必要で、多くの副作用がみられるのとは対照的です。
除菌に成功しますと、約半数の患者様で血小板数の回復が見られますので、ステロイドによる治療効果と遜色ありません。ITPに対する除菌療法は素晴らしい治療法です。
(血液専門医試験対策)
1)妊娠時のITP管理は問われやすいものと推測される。臨床的にも問題となりやすい。
2)ITPの(20〜)40%に抗リン脂質抗体が出現することを理解しておく必要がある。ITPに対して摘脾術を行うと血小板数回復に伴って、血栓症を誘発することがある。
3)そのため、ITP症例では、必ずループスアンチコアグラント、抗カルジオリピン抗体をチェックしておく必要がある。
(答)a
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 10:17 | 医師国家試験・専門医試験対策 | コメント(0) | トラックバック(0)
フラグミン(ダルテパリン)、クレキサン(エノキサパリン)とは:低分子ヘパリン
ダルテパリン & エノキサパリン(ともに、低分子ヘパリン)
推薦図書:「臨床に直結する血栓止血学」へパリン類などの抗凝固療法に関しても詳述されています。
日本で使用可能な低分子ヘパリン(low molecular weight heparin: LMWH)は、長らくダルテパリン(商品名:フラグミンなど)1剤のみでしたが、最近になり整形外科術後の深部静脈血栓症(deep vein thrombosis:DVT)予防目的にエノキサパリン(商品名:クレキサン)の使用が可能になりました。
アリクストラとともにクレキサンが、治療薬としてではなく予防薬として保険収載がなされたというのは、日本における保険制度の上で、まさに画期的な出来事ではないかと考えられます。
低分子ヘパリン(LMWH)の特徴としては、抗Xa/トロンビン活性比が未分画ヘパリンよりも高く(相対的にトロンビンを阻止しにくい)、血小板に対する影響が少なく出血の副作用が少ないことがあげられます。
また、未分画ヘパリンと異なり非特異的に血漿中蛋白(histidime-rich glycoprotein, fibronectin, vitronectin,血小板第4因子など)とほとんど結合しないために、ヘパリン不応例のような問題はあまりなく血中濃度も安定しやすいです。
また、未分画へパリンでみられるヘパリン依存性血小板減少症(HIT)や骨粗鬆症といった副作用もみられにくいです。
血中半減期は標準ヘパリンより若干長いですが、フラグミンでは24時間持続点滴による投与が基本です。クレキサンでは皮下注投与が行われています。
LMWHのモニタリングをどうするかについては、国際血栓止血学会雑誌において何回も誌上討論が行われたくらいであり一定の見解はありませんが、低体重の症例や腎機能障害の症例においては減量して使用すべきと言う点は、ほぼ共通した認識です。
関連記事(リンクしています)
DIC病型分類に関する欧文論文:Classifying types of disseminated intravascular coagulation: clinical and animal models. Journal of Intensive Care 2014, 2: 20.
・ヘパリン類(フラグミン、クレキサン、オルガラン、アリクストラ)
・低分子ヘパリン(フラグミン、クレキサン)
・オルガラン(ダナパロイド )
・フサン(線溶亢進型DICに対する特効薬)
・リコモジュリン(トロンボモジュリン製剤)
・NETセミナー:DICの病態・診断
・NETセミナー:DICの治療
・NETセミナー:血栓症と抗血栓療法のモニタリング
・プラビックス:パナルジン、プレタール、プロサイリン、ドルナー、ワーファリンとの比較(納豆は大丈夫か?)
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 05:55 | 抗凝固療法 | コメント(0) | トラックバック(0)