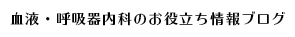【金沢大学血液内科進級試験過去問題(DIC)】兼:医師国家試験・専門医試験対策
金沢大学血液内科進級試験過去問題(2005年)
(設 問)(一部改変)
播種性血管内凝固症候群(DIC)の検査所見に関する記載として正しいものはどれか。
a. PT、APTT、フィブリノゲンともに正常であれば、DICを否定できる。
b. 線溶抑制型DICでは、血中プラスミノゲンアクチベーターインヒビター (PAI)活性が正常である。
c. 線溶亢進型DICでは、血中トロンビン-アンチトロンビン複合体(TAT)が著増する。
d. 線溶抑制型DICでは、血中プラスミン-α2プラスミンインヒビター複合体(PIC)が著増する。
e. 線溶亢進型DICでは臓器症状がみられやすい。
(ポイント)
a. PT、APTT、フィブリノゲンともに正常であってもDICのことはありうる。この場合、FDP&Dダイマー、TATは必ず上昇している。
b. 線溶抑制型DIC(代表的基礎疾患は、敗血症)では、線溶阻止因子PAIは著増する。
c. 線溶亢進型DICであっても、線溶抑制型DICであっても、DICであれば必ず著しい凝固活性化があるため、TATは著増する。
d. 線溶抑制型DICでは、PAIが著増して線溶が抑制されているため、PICの上昇は軽度にとどまる。
e. 線溶亢進型DICでは、多発した微小血栓は溶解しやすいため、微小循環障害をきたしにくい。出血症状は高度であるが、臓器症状はみられにくい。
(内科専門医試験対策)
FDP、Dダイマー、TAT、PICの意義は熟知している必要がある。
DIC診断上、PT、APTT、フィブリノゲンの重要性はやや落ちる。
TAT:凝固活性化マーカー。DICでは必ず上昇する。
PIC:線溶活性化マーカー。 線溶亢進型DICでは著増、線溶抑制型DICでは軽度上昇。
FDP&Dダイマー:血栓が分解して生じる分解産物。DICでは必ず上昇。
・播種性血管内凝固症候群(DIC)の病態、診断、治療(研修医/学生対応)
(血液専門医試験対策)
HPのNETセミナーに目を通しておこう!
・NETセミナー:DICの病態・診断
・NETセミナー:DICの治療
(答)C
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 19:38 | 医師国家試験・専門医試験対策 | コメント(0) | トラックバック(0)
L-アスパラギナーゼ(ロイナーゼ)と血栓症、DIC
L-アスパラギナーゼ(L-asparaginase:ロイナーゼ)は、急性リンパ性白血病などのリンパ性悪性疾患に対して使用される抗腫瘍薬です。
本薬は肝での蛋白合成を抑制しますが、それを反映して凝固第V、VII、VIII、IX、X、XI、フィブリノゲンといった凝固因子活性が低下します。加えて、凝固阻止因子であるアンチトロンビン、プロテインC、プロテインSも低下しますので、出血・血栓のいずれにも傾斜しやすい不安定な血栓止血病態となります。
従来、脳梗塞、深部静脈血栓症、肺塞栓などの報告が見られています。
小児科の急性リンパ性白血病を対象としたメタ解析によりますと、血栓症の発症頻度は5.2%と報告されています(1,752症例での検討)(文献←クリック)。
ほとんどの例で寛解導入療法時に血栓症を発症しています。また、L-アスパラギナーゼ(ロイナーゼ)を少量長期間投与する場合に特に発症頻度が高くなっているようです。
凝固異常の程度が強い場合は、新鮮凍結血漿により、凝固因子、凝固阻止因子の両者を補充し、血栓止血のバランスを安定化させることで対応可能です。
なお、管理人は、L-アスパラギナーゼ(ロイナーゼ)によりDICを発症した症例を経験しています。
【関連記事】
<特集>播種性血管内凝固症候群(図説)← クリック(シリーズ進行中!)
DIC関連記事(リンクしています)
・播種性血管内凝固症候群(DIC)の病態、診断、治療(研修医/学生対応)
・急性前骨髄球性白血病(APL)とDIC:ATRA、アネキシンII
・NETセミナー:DICの病態・診断
・NETセミナー:DICの治療
・ヘパリン類(フラグミン、クレキサン、オルガラン、アリクストラ)
・低分子ヘパリン(フラグミン、クレキサン)
・オルガラン(ダナパロイド )