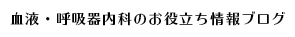金沢大学血液内科系統講義試験(輸血学)
本日の、血液内科試験に関しまして、輸血領域の問題&正答と、簡単な解説をアップします。
28.ABO型異型(不適合)赤血球輸血について誤っているものはどれか.一つ選べ.
a) 死亡率は約20%である.
b) 原因として最も多いのは輸血バッグの取り違えである.
c) ショックやDIC,腎不全に備える.
d) バイタルサインを測定したのち輸血を中止する.
e) 原則ICU管理とする.
(正答)d
(解説)ABO不適合輸血が判明した場合、まずは輸血を中止する。
29.輸血療法に関して正しいものはどれか.一つ選べ.
a) 体重40 kgの患者に赤血球製剤を2単位輸血すれば,Hbは約2 g/dL上昇する.
b) 輸血した血小板の約50%は脾臓に捕捉される.
c) 血清アルブミン値1.5 g/dLは,アルブミン投与の絶対適応である.
d) 新鮮凍結血漿は,融解後6時間以内に輸注する.
e) アルブミン投与後の血管回収率は通常100%である.
(正答)a
(解説)
a)赤血球製剤を1単位輸血するとHbは(40/患者体重)分増加する。患者体重40 kgの場合40/40=1 g/dL増加することになる。2単位の場合これを2倍すればよい。
b)輸血した血小板の約1/3はただちに脾臓に補足され破壊される。したがって、輸血した血小板のうち、血小板数増加に寄与するのは全体の約2/3である。
c)アルブミン投与の適応は「低アルブミン血症に伴う血漿膠質浸透圧低下・循環血漿量低下の改善」である。難治性腹水を伴う肝硬変や重症熱傷などがこれに相当する。低アルブミン血症だけではアルブミン投与の適応と言えない。
d)新鮮凍結血漿は、解凍後の失活を避けるため、原則として解凍後3時間以内に輸注する。
e)投与したアルブミンのうち血中にとどまるアルブミンの割合は血管回収率と呼ばれ、通常40%程度である。病態により変動するが、100%になることはない。残りは血管外へ漏出する。「血漿膠質浸透圧低下・循環血漿量低下の改善」に有益なのは、通常血中アルブミンに限られる。
30.下記の中で,手術前に赤血球輸血準備を考慮すべきものはどれか.一つ選べ.
a) 患者がRhD陽性
b) 患者がAB型
c) 不規則抗体陰性
d) 輸血の可能性が20%
e) 予想出血量400 mL
(正答)e
(解説)
以下のいずれかの場合、手術前に赤血球輸血準備を考慮する。
・輸血の可能性が30%以上
・予想出血量が400 mL以上
・RhD陰性
・不規則抗体陽性
したがって、答えはeとなる。
31.輸血前に調べなくてもよい感染症検査はどれか.一つ選べ.
a) HBs抗原
b) HBs抗体
c) HBc抗体
d) HCV抗体
e) HTLV-I抗体
(正答)e
(解説)
輸血前患者は下記検査を受けることが推奨されている。
・HBs抗原
・HBs抗体
・HBc抗体
・HCV抗体
・HCVコア蛋白
・HIV検査(同意が必要)
32.不規則抗体に関し正しいものはどれか.一つ選べ.
a) 不規則抗体は,Landsteinerの法則に従う血液型関連抗体である.
b) 不規則抗体は経産婦より未産婦の方が検出されやすい.
c) 不規則抗体は,抗A・抗B抗体を含む血液型関連抗体である.
d) 血液センターから供給される赤血球製剤は副試験不要である.
e) 不規則抗体は溶血の原因にならない.
(正答)d
(解説)
a)不規則抗体は、Landsteinerの法則に従わない血液型関連抗体である。
b)不規則抗体は、妊娠・出産・輸血などを契機に産生される。
c)抗A・抗B抗体はLandsteinerの法則に従う規則抗体である。
d)血液センターから供給される血液は、不規則抗体陰性が確認されているため、通常は副試験不要である。
e)不規則抗体は溶血性副作用を起こすことがある。
33.輸血後GVHDについて誤っているものはどれか.一つ選べ.
a) 血液製剤に含まれるリンパ球が患者を攻撃して起こる.
b) 致死率はほぼ100%である.
c) 年々増加している.
d) 近親者からの輸血を避けることは,予防策となる.
e) 新鮮血を避けることは,予防策となる.
(正答)c
(解説)
血液製剤への照射が行われるようになってから、輸血後GVHDは少なくなった。
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 20:40 | 医師国家試験・専門医試験対策 | コメント(0) | トラックバック(0)
金沢大学血液内科系統講義試験(平成20年12月2日)
本日の、金沢大学血液内科進級試験(系統講義試験)のうち、血栓止血領域の7題について、回答と簡単な解説をアップします。
なお、試験会場で見て回ったところでは、7〜8割くらいの人は、以下の7問に関しては満点だったと思います。
詳細な回答は、以前の過去問解説(右サイド医師国家試験・専門医試験対策のカテゴリー)も参照してもらえればと思います。
21.下記の疾患または病態のうち,検査所見の記載が正しいのはどれか.一つ選べ.
| 出血時間 | PT | APTT | Fbg | HPT | |
| a) 血友病 A | 延長 | 正常 | 延長 | 正常 | 正常 |
| b) von Willebrand病 | 延長 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| c) 先天性第VII因子欠損症 | 正常 | 延長 | 正常 | 正常 | 正常 |
| d) アスピリン内服 | 延長 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| e) Bernard-Soulier症候群 | 延長 | 正常 | 延長 | 正常 | 正常 |
PT:プロトロンビン時間
APTT:活性化部分トロンボプラスチン時間
Fbg:フィブリノゲン
HPT:ヘパプラスチンテスト
(正答)d
(解説)ごく若干名の方が、cを選択していましたが、HPTはVII、X、II因子を反映するため、先天性第VII因子欠損症では、HPTが低下します。
22.下記の疾患のうち出血,血栓の両者がみられる疾患・病態はどれか.一つ選べ.
a. 高Lp(a)血症
b. 高ホモシステイン血症
c. 異常フィブリノゲン血症
d. 先天性α2プラスミンインヒビター(α2PI)欠損症
e. 高プラスミノゲンアクチベータインヒビター(PAI)血症
(正答)c
(解説)異常フィブリノゲン血症では、出血、血栓の両者をおこしやすいです。ごく若干名の方が、 高ホモシステイン血症を選択していましたが、この疾患は血栓性病態です。
23.抗リン脂質抗体症候群(APS)に関する記載内容として正しいものはどれか.一つ選べ.
a. 血小板数,APTT,PTが正常で,抗カルジオリピン抗体が陰性であれば,APSを否定できる.
b. 40歳未満のAPS症例は例外的である.
c. 動脈血栓症では脳梗塞が最も多い.
d. 習慣性流産の若年女性に対しては,妊娠判明後ワルファリンによる抗凝固療法を行う.
e. ループスアンチコアグラント陽性例では,フィブリノゲンが上昇する.
(正答)c
(解説)動脈血栓症では脳梗塞が最も多いです。ほぼ全員が正答だったと思います。
24.播種性血管内凝固症候群(DIC)の記載として正しいものはどれか.一つ選べ.
a. 血小板数,フィブリノゲンともに正常であれば,DICを否定できる.
b. 急性前骨髄球性白血病に合併したDICでは,血中トロンビン-アンチトロンビン複合体(TAT)が著増する.
c. 線溶抑制型DICでは,血中トロンビン-アンチトロンビン複合体(TAT)が正常である.
d. 敗血症に合併したDICでは,血中プラスミン-α2プラスミンインヒビター複合体(PIC)が著増する.
e. 敗血症に合併したDICでは,フィブリノゲンが低下しやすい.
(正答)b
(解説)ごく若干名の方が、eを選択していましたが、敗血症では強い炎症反応のためフィブリノゲンは上昇し、DICを合併しても、フィブリノゲンは低下しにくいです。
25.血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)および溶血性尿毒症症候群(HUS)の両者に共通した所見の記載として正しいはどれか.一つ選べ.
a. 直接ビリルビンの上昇
b. ク−ムス試験陽性
c. 血清ハプトグロビンの上昇
d. 血清LDHの上昇
e. ADAMTS 13に対する自己抗体の出現
(正答)d
(解説)ごく若干名の方が、aを選択していましたが、直接ビリルビンではなく間接ビリルビンと見間違えてしまったのかも知れません。
26.血栓止血関連疾患の治療に関する記載として正しいのはどれか.一つ選べ.
a. 深部静脈血栓症の再発予防としては,アスピリンによる抗血小板療法が有効である.
b. 単純性紫斑病に対しては,ビタミンCの投与が半数例で有効である.
c. アレルギー性紫斑病に対しては,ビタミンKの投与が半数例で有効である.
d. 閉塞性黄疸を合併したビタミンK欠乏症に対しては,ビタミンKの内服が有効である.
e. インヒビターを有する血友病B症例の出血に対しては,遺伝子組換え活性型第VII因子製剤を投与する.
(正答)e
(解説)ごく若干名の方がaを選択していましたが、深部静脈血栓症の再発予防としては,ワルファリンによる抗凝固療法が有効です。
27.患者:22歳女性.抜歯後の止血困難の精査目的に来院した.血液検査は下記の通りであった.Hb 9.2 g/dL,血小板数 32.7万/μL,出血時間17分,PT 11.0秒,APTT 74.3秒,フィブリノゲン 322 mg/dL,FDP 1.9 μg/mL.妹には幼少時から頻回に鼻出血がみられる.「この22歳女性の疾患」と「血友病A」に共通しているのはどれか.一つ選べ.
a. 遺伝形式
b. 主な出血部位
c. 巨大血小板の出現
d. 血小板粘着能の低下
e. 血漿由来第VIII因子製剤(コンファクトF)が有効
(正答)e
(解説)この問題が一番難しいのではないかと思いましたが、ほとんどの人が正答でした。von Willebrand病と、血友病Aに共通しているのはどれかという問題です。血漿由来第VIII因子製剤(コンファクトF)は、von Willebrand因子も含有した第VIII因子濃縮製剤です。
血栓止血領域の7問は以上です。
全員が合格になっていることを祈っています。
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 16:52 | 医師国家試験・専門医試験対策 | コメント(0) | トラックバック(0)