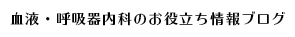全身性出血性素因の最初の検査
全身性出血性素因にある症例では、凝血学的検査を行う必要があります。
初めから、全ての検査を行うのは、非効率かつ経費がかかってしまいますので、何段階かに分けて検査を行うのが現実的です。
まず行うべきスクリーニング検査
1)血算(血小板数を含む)
2)プロトロンビン時間(PT)
3)活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)
4)フィブリノゲン
5)FDP
6)出血時間(必要に応じて、初めから血小板凝集能を行うこともあり)
理論的には、上記の検査によりほとんどの全身性出血性素因をスクリーニングしていることになります。ただし、スクリーニングされない出血性素因が2疾患あります。とてもまれな疾患です。
a)先天性第XIII因子欠損症:PT&APTTのいずれでもスクリーニングされません。
b)先天性α2PI欠損症:とても稀な疾患です。管理人は、この疾患の経験はありません。
ですから、第一段階の検査としては、1)〜6)を行うのが適当です。
ただし、注意が必要です。軽症の全身性出血性素因では、1)〜6)が正常になって見落とされることがあります。
たとえば、重症ではないvon Willebrand病では、APTTや出血時間が正常になってしまうことがあります。
ですから、幼少時からの鼻出血のように、von Willebrand病が疑われるような場合には、最初からvon Willebrand因子を測定する方が良いことがあります。
【リンク】
研修医の広場(金沢大学第三内科) ← 当科での研修の様子をご覧いただくことができます。
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 20:00 | 出血性疾患 | コメント(0)
ワーファリン:経口抗凝固薬、PT-INR
ワルファリン(経口抗凝固薬)
ワルファリン(商品名:ワーファリン)は、これまでは唯一内服可能な抗凝固薬でした(現在は、新規経口抗凝固薬がでましたので事情が変わっています)。ワルファリンはビタミンKの拮抗薬で、活性のあるビタミンK依存性凝固因子の産生を抑制することで抗凝固活性を発揮します。
ビタミンKのKの由来は、オランダ語のKoagulation(英語ではCoagulation)の頭文字に由来しています。文字通り凝固のためのビタミンと歴史的にも認識されてきました。また脂溶性ビタミンであり、その吸収には胆汁の存在を必要とします。
ビタミンK依存性凝固因子として、半減期の短い順番に第VII因子、第IX因子、第X因子、第II因子(プロトロンビン)の4つの凝固因子が知られています。これらの凝固因子は肝での生合成の最終段階で、ビタミンKの存在下で分子中のグルタミン酸のγ-カルボキシル化を生じ、このことによりカルシウム結合能を獲得し、血小板のリン脂質と結合できるようになります。
ワルファリン投与下やビタミンK欠乏状態では、グルタミン酸のγ-カルボキシル化が障害されて、PIVKA(protein induced by vitamin K absence)が出現します。
PIVKAはカルシウム結合が障害されており、凝固活性を有さず出血傾向をきたします。ただし、適切なモニタリングの下にワルファリンによって適度なビタミンK欠乏状態にすれば、あまり出血の副作用をきたすことなく血栓症の発症を抑制することが可能です。
ワルファリンは、心原性脳塞栓症、深部静脈血栓症、肺塞栓などの凝固血栓の病態に対して使用されます。ワルファリンを適切に使用することでこれらの血栓症の発症を有意に抑制することが可能です。特に、心房細動は高頻度にみられる不整脈であり、ワルファリン内服を必要とする患者数はかなり多いはです。
しかし、ワルファリンはPT-INR(古くはトロンボテスト)による適切なコントロールを行わないと出血の副作用が懸念されること、頻回の血液検査の煩雑さ、他の薬物との併用により効果が増強したり減弱したりすること、納豆などビタミンKの豊富な食物を摂取できないことなどの理由により、ワルファリン治療がなされるべきでありながらアスピリンなど他剤で代用されてきた事例が少なくありませんでした(ワルファリンを用いるべき病態に対してアスピリンを用いても十分な効果が期待できないことが知られているにもかかわらずです)。
比較的最近、複数スポーツ監督者の心原性脳塞栓症の報道が多くあったことなどに伴ってか、この疾患に対する国民の関心が格段に高まっています。
ワルファリンが用いられるべき患者に対して本薬の処方件数が増加するのは国民全体の健康に貢献すると考えられますが、出血の副作用は最小限に抑制することが重要です。
現在、院内でPT-INRの即日検査が可能な医療機関は中規模以上の病院と考えられますが、小規模病院や開業医でも簡便にPT-INRのチェックが可能な機器の登場は、本薬が適正に内服される上でも極めて意義が高いです。
この点、約1分で結果を出せるPT-INR簡易・迅速測定装置 「コアグチェック XS」の存在はありがたいです。
関連記事
・ 血液凝固検査入門:インデックスページ ← クリック(全記事、分かり易く図解)
関連記事(リンクしています)
・ヘパリン類(フラグミン、クレキサン、オルガラン、アリクストラ)
・低分子ヘパリン(フラグミン、クレキサン)
・オルガラン(ダナパロイド )
・フサン(線溶亢進型DICに対する特効薬)
・リコモジュリン(トロンボモジュリン製剤)
・NETセミナー:DICの病態・診断
・NETセミナー:DICの治療
・NETセミナー:血栓症と抗血栓療法のモニタリング
・プラビックス:パナルジン、プレタール、プロサイリン、ドルナー、ワーファリンとの比較(納豆は大丈夫か?)
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 06:28 | 抗凝固療法 | コメント(1) | トラックバック(0)